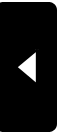2016年01月05日
サラセニアの鉢底
今年のサラセニアの植え替え作業でこれまで試験的に行っていた鉢底の植え込み方に、
良好な結果が出ました。以前、大阪屋さんのブログで鉢底に軽石を敷くとサラセニアが
根腐れすると紹介されていて、その際私もコメントしていましたが、この根腐れ現象には
すごくうなずいていました。我が家でも同様の現象が起きており、どうも我が家ではS.
フラバを中心に軽石に降れる根の先端が枯れ込むのです(S.アラタは元気)。
そこで私の場合、鉢底にベラボンSサイズを敷くようにしました(一部はMサイズを使用)。
鉢底穴が大きい場合はSサイズのベラボン用土が流れ出ないようにヘゴチップを使って
鉢底穴を塞ぎました。ヘゴチップ、ベラボンを選択したのは水ゴケより腐りにくい有機質の
植込み材料だからです。実はこの時、植込み材料にもこの後書く通り、色々考えていまし
た。
写真の株は4号の超ロングポットに植えていました。超ロングポットもここ3,4年使用して
いますがポットが深すぎる事により根が酸欠になる事は今の所、無さそうです。
むしろこの深さでも根は軽々鉢底まで伸ばし、いったいサラセニアの根ってどこまで伸び
るんでしょうね~。

最底部はヘゴチップを敷いていましたが、全く根腐れすることなく根が健全に伸びていま
した。

前々から根腐れの原因は鉢底の植込み素材の種類にあるのではないかと思っていまし
た(有機質、無機質の違い?)ので、試験的に鉢底の植込みを変える時はあえて無機質
の軽石と異なる有機質のベラボンやヘゴチップを使用してみました。
結果は、ベラボンSサイズ、ヘゴチップ良好!写真を撮ってませんが、ベラボンのMサイズ
でも同様に根が健全に伸びていたので、良好!
どうやら鉢底の植込み素材の種類(有機質、無機質)の違いが根腐れの原因に大きく寄与
しているのではないかという個人的結論に達しました。
今年のサラセニアの植え替えは全ての株にて軽石による鉢底植込みは止めました。ベラボ
ン、ヘゴチップのみ使用して鉢底は植えこんでいます。ベラボンはMサイズを切らしているの
で、大きさはSサイズを使用しています。
もう一つ、水ごけ植えって毎年植え替えないといけないと思い込みがちですが、上の写真は
2年植え替えていませんが、水ゴケは綺麗なままでした。もちろん繊維もしっかり残っていま
す。2年植え替えなくてもこの状態ですから、うまくいけば3年までは植え替えなくてもイケる
かも知れません。もちろん、最初に使用する水ゴケのランクはAAA以上としています。
まあ3年もすれば芽先が鉢の縁に達する事で植え替える事になるのが多いと思いますが・・・。
(^^;
良好な結果が出ました。以前、大阪屋さんのブログで鉢底に軽石を敷くとサラセニアが
根腐れすると紹介されていて、その際私もコメントしていましたが、この根腐れ現象には
すごくうなずいていました。我が家でも同様の現象が起きており、どうも我が家ではS.
フラバを中心に軽石に降れる根の先端が枯れ込むのです(S.アラタは元気)。
そこで私の場合、鉢底にベラボンSサイズを敷くようにしました(一部はMサイズを使用)。
鉢底穴が大きい場合はSサイズのベラボン用土が流れ出ないようにヘゴチップを使って
鉢底穴を塞ぎました。ヘゴチップ、ベラボンを選択したのは水ゴケより腐りにくい有機質の
植込み材料だからです。実はこの時、植込み材料にもこの後書く通り、色々考えていまし
た。
写真の株は4号の超ロングポットに植えていました。超ロングポットもここ3,4年使用して
いますがポットが深すぎる事により根が酸欠になる事は今の所、無さそうです。
むしろこの深さでも根は軽々鉢底まで伸ばし、いったいサラセニアの根ってどこまで伸び
るんでしょうね~。

最底部はヘゴチップを敷いていましたが、全く根腐れすることなく根が健全に伸びていま
した。

前々から根腐れの原因は鉢底の植込み素材の種類にあるのではないかと思っていまし
た(有機質、無機質の違い?)ので、試験的に鉢底の植込みを変える時はあえて無機質
の軽石と異なる有機質のベラボンやヘゴチップを使用してみました。
結果は、ベラボンSサイズ、ヘゴチップ良好!写真を撮ってませんが、ベラボンのMサイズ
でも同様に根が健全に伸びていたので、良好!
どうやら鉢底の植込み素材の種類(有機質、無機質)の違いが根腐れの原因に大きく寄与
しているのではないかという個人的結論に達しました。
今年のサラセニアの植え替えは全ての株にて軽石による鉢底植込みは止めました。ベラボ
ン、ヘゴチップのみ使用して鉢底は植えこんでいます。ベラボンはMサイズを切らしているの
で、大きさはSサイズを使用しています。
もう一つ、水ごけ植えって毎年植え替えないといけないと思い込みがちですが、上の写真は
2年植え替えていませんが、水ゴケは綺麗なままでした。もちろん繊維もしっかり残っていま
す。2年植え替えなくてもこの状態ですから、うまくいけば3年までは植え替えなくてもイケる
かも知れません。もちろん、最初に使用する水ゴケのランクはAAA以上としています。
まあ3年もすれば芽先が鉢の縁に達する事で植え替える事になるのが多いと思いますが・・・。
(^^;
Posted by senda at 22:53│Comments(8)
│食虫植物
この記事へのコメント
初めまして
ブログ、楽しく読ませていただきました。
食虫植物栽培について非常にためになる内容が多いので
勉強になります。サラセニアの鉢底に関する考察は目からうろこでした。自己責任であれこれ試してみようと思います。
自分は食虫植物の自生地がほとんど無い埼玉県に住んでいますがブログ主さんのご実家の滋賀県が羨ましいです。
ブログ、楽しく読ませていただきました。
食虫植物栽培について非常にためになる内容が多いので
勉強になります。サラセニアの鉢底に関する考察は目からうろこでした。自己責任であれこれ試してみようと思います。
自分は食虫植物の自生地がほとんど無い埼玉県に住んでいますがブログ主さんのご実家の滋賀県が羨ましいです。
Posted by HanasakaG at 2016年01月06日 15:23
私も鉢底の種類によって根腐れするって聞くのは初めてでした。
sarracenia以外も同じことが起きるのでしょうか?
sarracenia以外も同じことが起きるのでしょうか?
Posted by 鍵の君 at 2016年01月06日 19:44
HanasakaGさん、こんにちは。
サラセニアの鉢底の考察に関しては個人的な見解なので、
あくまで参考情報と捉えて下さい。
(^^;
食虫植物は一般的に根が貧弱な種類が多い中、サラセニアはこれだけ根が発達するので、
出来るだけ根の発育状態には気を付けたいと思っていました。
埼玉ですと、自生地と言っていいのか分かりませんが、国内唯一のムジナモの自生地を
一回見てみたいなあっと思っています。
これからもよろしくお願いします。
サラセニアの鉢底の考察に関しては個人的な見解なので、
あくまで参考情報と捉えて下さい。
(^^;
食虫植物は一般的に根が貧弱な種類が多い中、サラセニアはこれだけ根が発達するので、
出来るだけ根の発育状態には気を付けたいと思っていました。
埼玉ですと、自生地と言っていいのか分かりませんが、国内唯一のムジナモの自生地を
一回見てみたいなあっと思っています。
これからもよろしくお願いします。
Posted by senda at 2016年01月07日 05:31
at 2016年01月07日 05:31
 at 2016年01月07日 05:31
at 2016年01月07日 05:31鍵の君さん、こんにちは。
鉢底石を敷くと確かに我が家ではS.フラバが毎年、水ごけ部は元気な白い根を張るのに、
軽石に触れる根の先端部だけが黒く腐り込むので、何か鉢底部に原因があるんではないのかな~?と思っていました。
ただ、水ごけより砂利系でサラセニアを植え付ける趣味家も多いと思いますので、
砂利系で育てている場合は単純に鉢底石の部分だけが枯れ込むのかは不明ですね。
この辺は追加実験しても面白そうかも知れません。
なお、サラセニア以外は今の所、我が家では鉢底石が原因と思われる根腐れ経験はありません。
鉢底石を敷くと確かに我が家ではS.フラバが毎年、水ごけ部は元気な白い根を張るのに、
軽石に触れる根の先端部だけが黒く腐り込むので、何か鉢底部に原因があるんではないのかな~?と思っていました。
ただ、水ごけより砂利系でサラセニアを植え付ける趣味家も多いと思いますので、
砂利系で育てている場合は単純に鉢底石の部分だけが枯れ込むのかは不明ですね。
この辺は追加実験しても面白そうかも知れません。
なお、サラセニア以外は今の所、我が家では鉢底石が原因と思われる根腐れ経験はありません。
Posted by senda at 2016年01月07日 05:45
at 2016年01月07日 05:45
 at 2016年01月07日 05:45
at 2016年01月07日 05:45早々の返信をありがとうございます。
はい、もちろん全て自己責任で参考にさせてもらいます。
サラセニアに関してうちでは鉱物系主体でそれにベラボンを混ぜる組み合わせで2~3年毎の植え替えを行なっていました。用土の種類のみならず鉢の深さも根の発育にかなり重要みたいですね。ありがとございました。
羽生の自生地はうちからは車で一時間ほどの所ですが、保護された自生地は立ち入り禁止でムジナモを見る事は出来ません。そのかわり隣接する淡水魚水族館で展示物を見る事が出来ます。親水公園となっている部分の池には多数のタヌキモが繁殖します。タヌキモに詳しくないので判らないのですが一種類では無いように感じまたずっと以前には全く繁殖していなかったので移植されたものと思われます。
一般の方はタヌキモを見て「これがムジナモかぁ」と言っていますね。
此方こそ、これからもよろしくお願いします。
はい、もちろん全て自己責任で参考にさせてもらいます。
サラセニアに関してうちでは鉱物系主体でそれにベラボンを混ぜる組み合わせで2~3年毎の植え替えを行なっていました。用土の種類のみならず鉢の深さも根の発育にかなり重要みたいですね。ありがとございました。
羽生の自生地はうちからは車で一時間ほどの所ですが、保護された自生地は立ち入り禁止でムジナモを見る事は出来ません。そのかわり隣接する淡水魚水族館で展示物を見る事が出来ます。親水公園となっている部分の池には多数のタヌキモが繁殖します。タヌキモに詳しくないので判らないのですが一種類では無いように感じまたずっと以前には全く繁殖していなかったので移植されたものと思われます。
一般の方はタヌキモを見て「これがムジナモかぁ」と言っていますね。
此方こそ、これからもよろしくお願いします。
Posted by HanasakaG at 2016年01月07日 07:59
HanasakaGさん、こんにちは。
ムジナモの自生地、中々自由な見学は難しそうですね。
昨年は一般の見学会もあったようなので、今年もあれば参加してみたいと思っています。
(^^ゞ
ムジナモの自生地、中々自由な見学は難しそうですね。
昨年は一般の見学会もあったようなので、今年もあれば参加してみたいと思っています。
(^^ゞ
Posted by senda at 2016年01月08日 04:51
at 2016年01月08日 04:51
 at 2016年01月08日 04:51
at 2016年01月08日 04:51なかなか調子良いですね~。
私の同じ結果になっているのでこの頃は鉢底石をほとんど使っていません。
この傾向は砂利系でも同じなので果たして何がいけないのか・・・。
後は腰水の状態が良ければ申し分ないというところでしょうか、ベラボンでも水質が悪いと2年ぐらいで劣化して根腐れの原因になるようです。
私の同じ結果になっているのでこの頃は鉢底石をほとんど使っていません。
この傾向は砂利系でも同じなので果たして何がいけないのか・・・。
後は腰水の状態が良ければ申し分ないというところでしょうか、ベラボンでも水質が悪いと2年ぐらいで劣化して根腐れの原因になるようです。
Posted by 大阪屋 at 2016年01月08日 10:08
大阪屋さん、明けましておめでとうございます。
今年もよろしくお願いします。
関西集会は今年も行きますよ~。関西に帰れるのは確実ですが、何月に帰れるかは未定です。
まあ、多少延びるぐらいは覚悟していますが・・・。
(^_^;
サラセニアは砂利系でも同じ現象が出ますか、、、。
鉢底の根腐れ現象って集会、ウェブでもあまり聞かないので、まだまだ情報が少ないですね。
ベラボンも腐る事はありそうなので、腰水の水質は気を付けたいと思います。
今年もよろしくお願いします。
関西集会は今年も行きますよ~。関西に帰れるのは確実ですが、何月に帰れるかは未定です。
まあ、多少延びるぐらいは覚悟していますが・・・。
(^_^;
サラセニアは砂利系でも同じ現象が出ますか、、、。
鉢底の根腐れ現象って集会、ウェブでもあまり聞かないので、まだまだ情報が少ないですね。
ベラボンも腐る事はありそうなので、腰水の水質は気を付けたいと思います。
Posted by senda at 2016年01月09日 09:16
at 2016年01月09日 09:16
 at 2016年01月09日 09:16
at 2016年01月09日 09:16